![]()
<指揮者>
<作曲家>
<工学研究者>
<関連音楽大学>
<関連音楽団体・学会>
日本現代音楽協会Facebook
<お店>
******
ホアキン・M.ベニテズ Joaquim M. Benitez 先生が2015年6月10日ご逝去され,6月16日カトリック麹町聖イグナチオ教会にて葬儀ミサが行われました.6月6日に75歳のお誕生日を迎えられたばかりでした.安らかな眠りをお祈り致します.
<私にとって> ベニテズ先生は膨大な知識,他に類をみない頭の良さ,そして数々の偉業を成し遂げられた偉大な方で,愛情深く慈しみ深く,人としてとても素晴らしい方で,私にとっては最も尊敬申し上げ,とてもとても大切な恩師です.先生に師事できたことは本当に幸せです.
<先生から頂いたお言葉>先生のひと言ひと言が私の宝です.また,博士号を頂いたとき「おまえを私の弟子と認める」と言って頂けたことも嬉しかったです.
<学問に対する先生の姿勢>先生は学問に対しては非常に真摯に向き合われ,研究に対する厳しい目をお持ちでした.博士課程の学生の論文指導では,本当に真剣にご指導して下さいました.先生のご指導は世界水準の論文指導なので,私の博論の謝辞にそれを書きたいと申し上げましたときに,「恥ずかしいからやめてくれ,おまえはオーバーじゃないか?」とおっしゃって,とうとうご承諾頂けませんでした.
<先生との思い出> 先生は根はとても陽気な方で,博士課程の後輩たちとご一緒に私の自宅にお招きし,ご馳走を作ってご一緒にお食事して頂いたときも,とても楽しくご歓談され,いろいろな為になるお話を聞かせて頂きました.その前に自動車で広島大学西条キャンパスに立ち寄ってご案内したときも,みんなで大はしゃぎでした.先生のお誕生日のとき,いつも博士課程の学生は他の門下の学生も大勢集まって,お祝いパーティで大盛り上がりでした.その後,博士課程の学生のMさんのご自宅でもクリスマスなどのパーティをたびたびして下さって,みんなと一緒に楽しくわいわいとご歓談されました.
<ベニテズ先生へ> ベニテズ先生,先生はずっと私の心の中にあられ,ずっと先生のことを思い続けております.どうぞ天国から私たちを見守って下さい.安らかな眠りをお祈り致します.
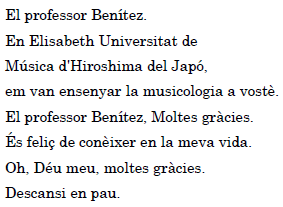
<エリザベト音楽大学ホームページより転載>
略歴
ホアキン・ベニテズ師は1940年スペイン国生まれ、1957年にカトリック修道会のイエズス会に入会し、1973年カトリック司祭に叙階。
1963年スペイン国聖フランシスコボルジア大学哲学学部卒業、1964年アメリカ合衆国Boston College in Shadowbrook (Mass.)、1967年上智大学日本研究センター卒業、1971年東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了、1974年同大学院博士課程単位取得満期修了。
1972年よりエリザベト音楽大学で教鞭をとり、1974年専任講師、1978年助教授、1985年教授。1981年学校法人エリザベト音楽大学理事、1986年エリザベト音楽大学第3代学長に就任(1996年7月10日まで)。また、エリザベト音楽大学大学院音楽研究科長、附属図書館長も務めた。2010年4月名誉教授。
専門は音楽学。学長在任中に大学院音楽研究科修士課程及び博士後期課程を設置。博士後期課程開設は東京芸術大学に次いで2大学目、私立の音楽大学では初めてであり、エリザベト音楽大学を音楽の専門教育を行う高等教育機関として位置づけ、海外から多くの音楽家を招聘するなど学生の教育・研究のために尽力した。
日本音楽学会、美学会、国際音楽資料情報協会日本支部、東洋音楽学会に所属、日本音楽図書館協議会理事長・顧問、講談社「ニュー・グローヴ世界音楽大事典」編集委員、イギリスの現代音楽誌 ”Contemporary Music Review” 日本編集委員会委員、IAML(国際音楽資料情報協会)東京国際会議1988実行委員会副委員長、MLAJ(日本音楽図書館協議会)広島国際会議1988実行委員会委員長、広島国際フェスティバル会長、中国ユース・ピアノコンクール(中国新聞社主催)企画委員、広島文化デザイン会議顧問等を務め、日本における学術振興にも貢献した。

<研究者リサーチマップのホームページより>
研究キーワード:
音楽美学,音楽史,音楽学
研究分野:
哲学/美学・美術史
学歴:
- 1974年 東京大学 人文科学研究科 美学芸術学専門音楽美学専攻
- 1963年 聖フランシスコ・ボルジア大学 哲学部
委員歴:
1985年 - 1989年 音楽図書館協議会(MLAJ)(Music Library Association of Japan(MLAJ)) 理事長
論文:
仏教唱歌の創成と変遷-明治22?40年出版の7冊の楽譜付き仏教唱歌集を中心に-(共著)
エリザベト音楽大学研究紀要[広島, エリザベト音楽大学] XXI 49-61 2001年
明治四〇年出版『讃佛歌』における讃美歌の借用(単著)
東洋音楽研究[東京,東洋音楽学会] (66) 1-15 2001年
讃仏歌の創成と変還−明治40〜大正12年出版の讃仏歌集及び『らいさん』の研究−(共著)
エリザベト音楽大学研究紀要[広島,エリザベト音楽大学] XXII 43-55 2002年
讃仏歌の創成-明治40年出版『讃佛歌』の研究-(単独発表)
東洋音楽学会第51回大会[金沢, 金沢市文化ホール10月8日] 2000年
明治四〇年〜大正十二年出版の讃仏歌における讃美歌の借用について(単独発表)
広島芸術学会第57回例会[広島,エリザベト音楽大学12月15日] 2001年
Contemporary Music Reviewの特集号 "Flute and Shakuhachi" 編著 (共編)
Contemporary Music Review [London, Harwood Academic Publishers] 8(2) 259 1994年
A Survey of Contemporary Music for Shakuhachi by Japanese Composers (共著)
Contemporary Music Review [London, Harwood Academic Publishers] 8(2) 239-256 1994年
Contemporary Music Reviewの特集号"Gagaku and Serialism : A Portrait of Matsudaira Yoritsune"編著(共編)
Contemporary Music Review [London, Harwood Academic Publishers] 17(4) 100 1998年
L'oreille orientale et la musique de l'Ouest : Entretien avec Jo Kondo 仏文 (共著)
Etudes [Paris, Etudes] (3894) 369-377 1998年
"Chormusik" "Religiose Musik : Christliche Musik" (単著)
Japan-Handbuch [Wiesbaden, Franz Steiner Verlag] hrsg. von Horst Hammitzsch (事典) 1199-1202,1280-1284 1981年
著書:
現代音楽を読む-エクリチュールを超えて-(単著)
東京,朝日出版社 1981年
ヨーロッパ音楽の歴史-西洋文化における芸術音楽の伝統-(共訳)
東京,朝日出版社 1984年
十八世紀音楽思想の一断面-エクシメーノの『音楽の起源と規則』の場合(単著)
精神と音楽の交響-西洋音楽美学の流れ[東京,音楽之友社]今道友信編 1997年
Collective Improvisation in Contemporary Western Art Music (単著)
The Oral and the Literate in Music [Tokyo, Academia Music] Edited by Y. Tokumaru and O. Yamaguchi
1986年
所属学会:
日本音楽学会 , 美学会 , 東洋音楽学会 , 国際音楽資料情報協会(IAML)(International Association of Music Libraries,Archives and Documentation Centres (IAML)) , 音楽図書館協議会(MLAJ)(Music Library Association of Japan(MLAJ))
研究テーマ:
現代音楽の美学,17、18世紀ヨーロッパの音楽思想,音楽書誌学,明治、大正時代の仏教音楽
******